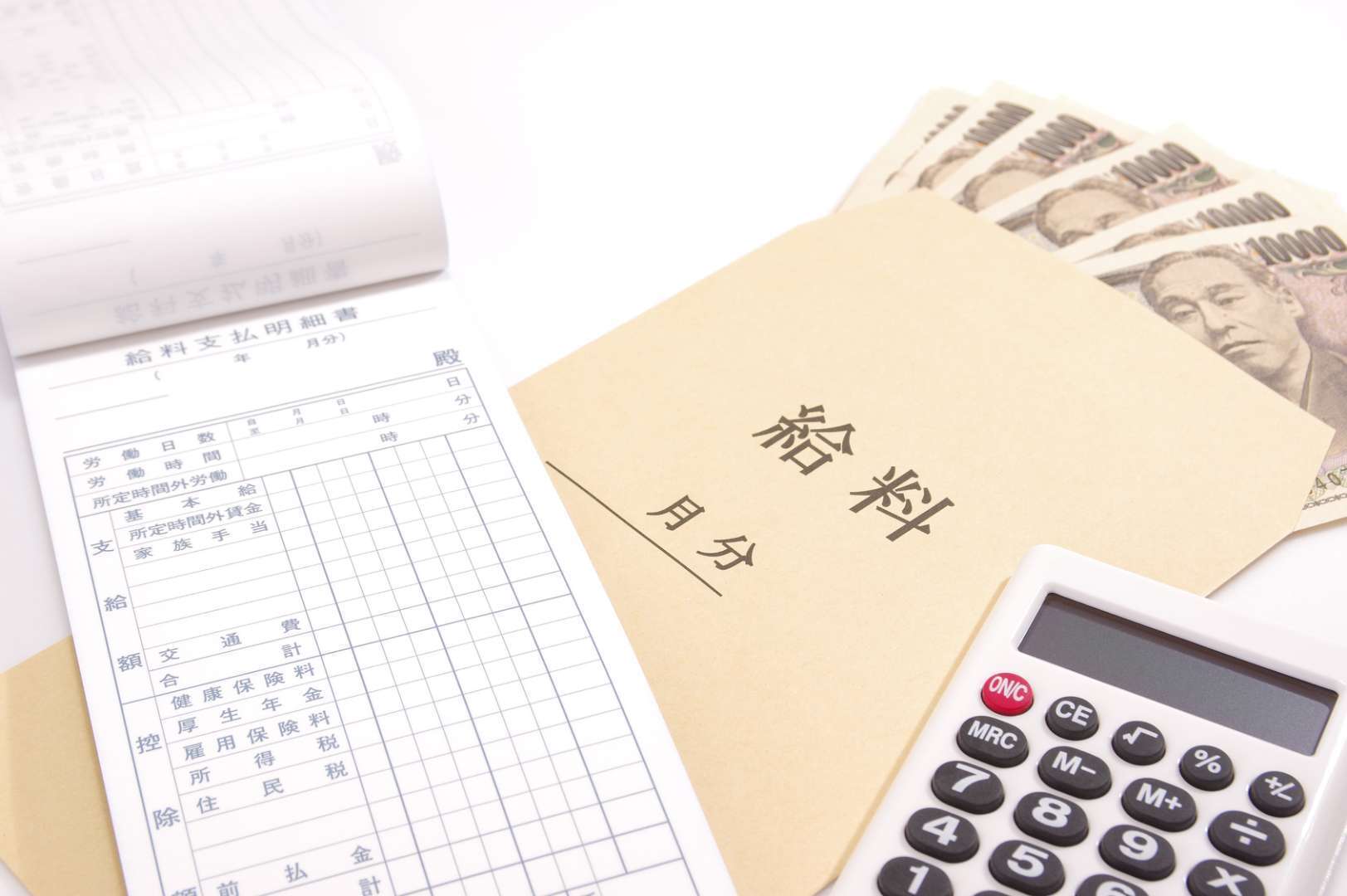「2級施工管理技士を取れば、ちゃんと稼げるのか?」──現場で働きながら、あるいは資格取得を考えている方の多くが一度は抱く疑問です。特に建設業界は、資格が収入やポジションに直結する職種が多く、「2級」でも十分通用するのか、自分の将来にどう影響するのかが気になるところでしょう。
インターネットで「2級施工管理技士 年収」と検索すると、ばらつきのある情報が並び、期待と不安が入り混じった気持ちになるかもしれません。「400万円台?」「いや600万円くらいじゃ?」といった声もあれば、「資格があっても安月給」という投稿も見受けられます。
この記事では、あいまいな噂や印象論ではなく、求人情報や統計、実務上の傾向をもとに、“実際のところどうなのか”を丁寧に読み解いていきます。資格を取るかどうか迷っている人、今後のキャリアに不安を抱えている人が、自分の道を少しでもクリアに描けるよう、正直な情報をお届けします。
2級建築施工管理技士の平均年収は?年代・地域・業種で見るリアルな相場
「2級施工管理技士の年収は〇〇円」と一言で言い切るのは難しいのが実情です。なぜなら、収入は勤務先の規模や地域、扱う工事の種類、年齢・経験年数などで大きく変わるからです。それでも傾向として言えるのは、全国的に見て年収は400〜550万円台がひとつのボリュームゾーンであるということ。厚生労働省の統計や大手求人サイトの掲載情報からも、このレンジに集中しています。
たとえば、首都圏での施工管理職(2級資格保持者)の募集を見ると、経験5年以上で年収500〜600万円台という事例も珍しくありません。一方で、地方の小規模工務店などでは350〜400万円台にとどまることもあり、同じ資格でも地域差は顕著です。また、公共工事中心の会社と民間リフォーム中心の会社では、繁忙期や残業時間、待遇にばらつきがあることも影響します。
もうひとつ注目すべきは年齢との関係です。20代後半〜30代前半で400万円前後、40代になると500〜600万円に届くケースが増え、役職がつくとさらに上昇します。ただし、年収が上がるかどうかは、単に資格を持っているかではなく、現場経験の深さやマネジメント力の有無が大きな差を生む点も忘れてはいけません。
次章では「なぜ“資格があるのに安い”と感じる人がいるのか?」その背景を紐解いていきます。
「安い」と言われる理由と、それでも資格取得が有利になる理由とは?
ネット上では「2級施工管理技士は取っても年収が上がらない」「安月給のまま」という声を見かけることがあります。そう感じる理由の一つは、資格取得そのものが即座に給料に反映されるとは限らないという現実です。特に小規模な工務店や家族経営の現場では、資格の有無よりも「現場で使えるかどうか」が評価の基準となり、資格手当が付かない、あるいは微々たる額しかつかないこともあります。
また、施工管理の現場は体力勝負の面もあり、若手であれば無資格でも現場に出て稼ぐことができるため、資格の価値を実感しにくい環境にある人も少なくありません。逆に、現場責任者を任されたり、協力業者との調整や書類管理まで求められるようになると、資格の有無が責任範囲や昇進に直結するようになります。
つまり、「資格を持っていても安い」と感じる人の多くは、まだ資格を“活かすポジション”にいない可能性があります。これは裏を返せば、今後のキャリア次第で収入も変わるということです。建設業界では、法令上の要件として一定規模の工事に施工管理技士が必要になるため、会社にとっては有資格者の存在が契約の前提になる場面も増えています。
さらに、建設業法の改正により、技術者の配置や管理体制に厳格な条件が設けられるようになり、資格を持つ人の価値が年々高まっているのも事実です。ただ現場に出ているだけでは手に入らない「評価される肩書き」として、2級施工管理技士は確実に武器になります。
次章では、この資格を活かして年収を上げていく具体的な方法に踏み込みます。
どうすれば年収を上げられる?実務経験・役職・現場の違いがカギ
「2級施工管理技士の資格は取ったけど、どうすれば給料が上がるのか分からない」──そんな声をよく聞きます。年収を上げるには、資格取得の“その先”でどんな行動を取るかが決定的に重要です。最初に意識すべきなのは、実務経験と役職です。現場での実務経験を積み、主任技術者や現場代理人といった責任あるポジションを担うことで、評価や手当が大きく変わります。
たとえば、同じ資格でも「図面が読める」「工程をまとめられる」「協力業者との調整ができる」といったスキルがある人材は、会社からの信頼度も高くなり、昇給のチャンスが増えます。逆に、資格は持っていても実務の幅が狭いままでは、給与はなかなか上がりません。つまり、年収アップには「現場力」と「人をまとめる力」の両方が問われているのです。
また、配属される現場の規模や種類によっても収入は変わります。公共工事や大規模案件では、元請として現場管理を担う場面が多く、責任とともに報酬も上がりやすくなります。一方、戸建てリフォームや下請け業務では、責任範囲が限定されていることもあり、給与も控えめになりがちです。そのため、意識的に「どんな現場で」「どう成長するか」を考えることが年収向上には欠かせません。
加えて、建設業界は高齢化が進み、若手の施工管理職は引く手あまたの状態です。20代〜30代で資格を持っているだけで、他社からスカウトを受ける可能性もあります。職場環境に伸びしろを感じない場合は、転職によって待遇を改善するのも一つの手段です。
次章では、そうしたキャリア選択の一つとして「1級との年収差」や進み方を見ていきます。
なお、当社での取り組みや働く環境はこちらからご覧いただけます。
▶︎ https://www.t-t-home.com/about_us
1級と2級の年収差はどれくらい?キャリアパスを考える判断材料に
2級施工管理技士を取得した人が次に考えるのが「1級を取った方がいいのか?」という問いです。その判断にあたって最も気になるのが、年収にどれほど差が出るのかという点でしょう。実際、1級と2級では、扱える工事の規模が法律上で明確に区別されているため、任される現場の責任範囲やポジションに大きな違いが生まれます。
たとえば、2級施工管理技士が主に担当するのは中小規模の工事や木造住宅などが中心ですが、1級を取得すると国交省が発注する大規模公共工事の現場代理人にもなれます。その結果、1級保持者は年収600〜750万円台が中心層となり、現場経験や役職によっては800万円以上を目指せる場合もあります。一方、2級保持者の場合は400〜550万円が多く、昇給の幅も限定されがちです。
もちろん、資格を取ったからといって自動的に年収が跳ね上がるわけではありません。しかし、**「昇進のための条件」や「現場配置の法定要件」**として使われる場面が多いため、1級の保有は確実にポジションの選択肢を広げてくれます。特に、会社全体で施工管理の技術者が不足している現場では、1級の資格保持者はより優遇されやすくなります。
ただし、1級の試験は2級に比べて難易度が格段に高く、学習時間や実務経験も求められます。だからこそ、まず2級を活かし、年収を安定させながら計画的に1級を目指すというステップが、多くの人にとって現実的です。
いまの職場での評価や将来の待遇に不安があるなら、まずは今の働き方を見直し、次の一歩をどう踏み出すかを考えてみてください。
▶︎ https://www.t-t-home.com/about_us
後悔しないために──資格取得とキャリア設計は“セット”で考えるべき理由
2級施工管理技士は、取得しただけで未来が劇的に変わる資格ではありません。けれども、使い方しだいで確実にキャリアの選択肢を増やし、年収アップの足がかりになります。だからこそ、資格をゴールにするのではなく、「どんな現場で何を積み重ねるか」「どんなポジションを目指すか」といったキャリア設計とあわせて考える視点が欠かせません。
現場で経験を重ねながら、責任ある立場に挑戦する。さらに上を目指して1級の取得を視野に入れる。その積み重ねが、結果として年収や働き方の自由度を広げていく道につながります。今の働き方にモヤモヤを感じているなら、環境そのものを見直すことも選択肢に入れてみてください。